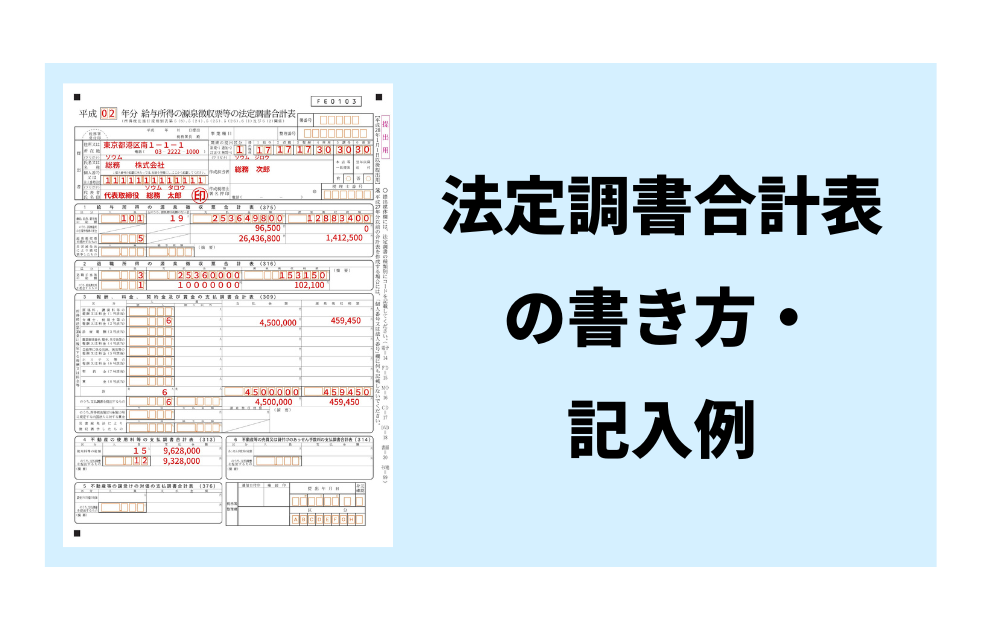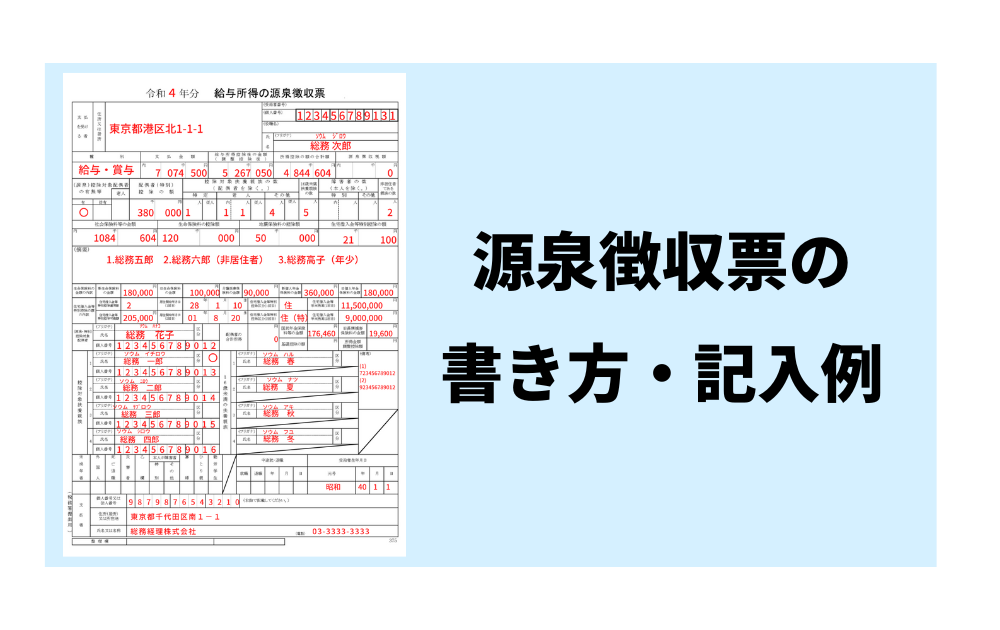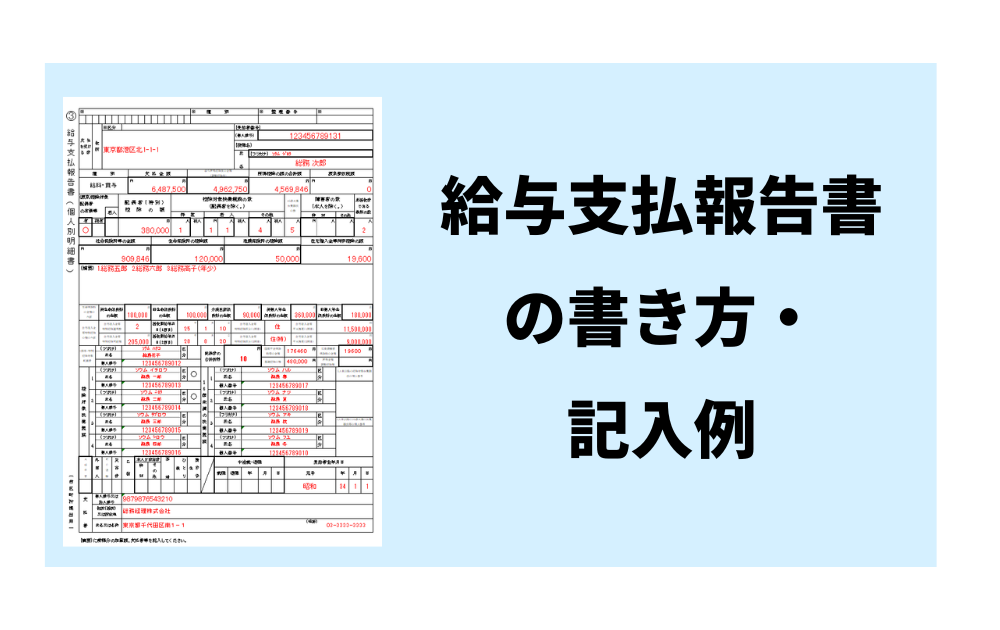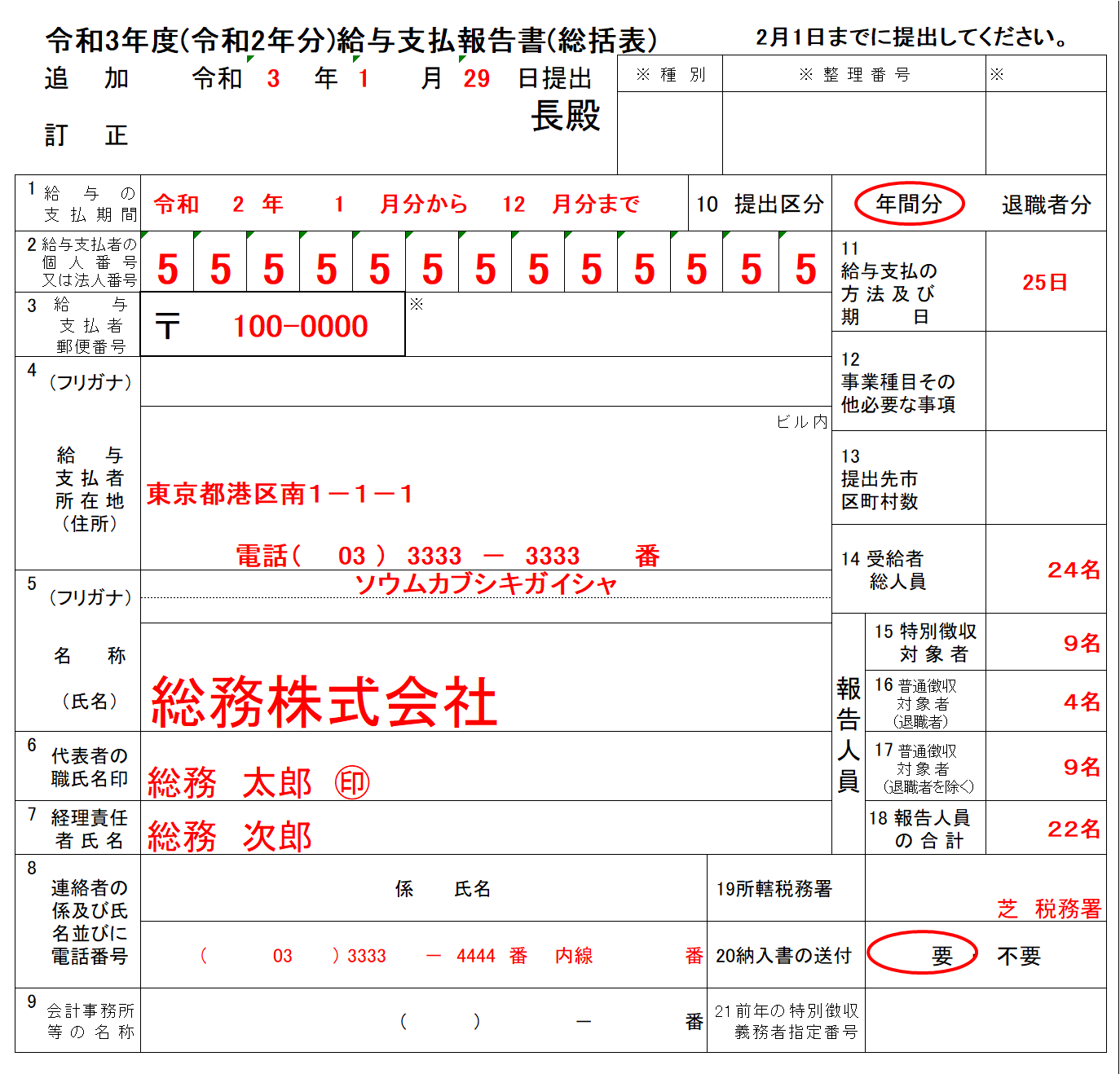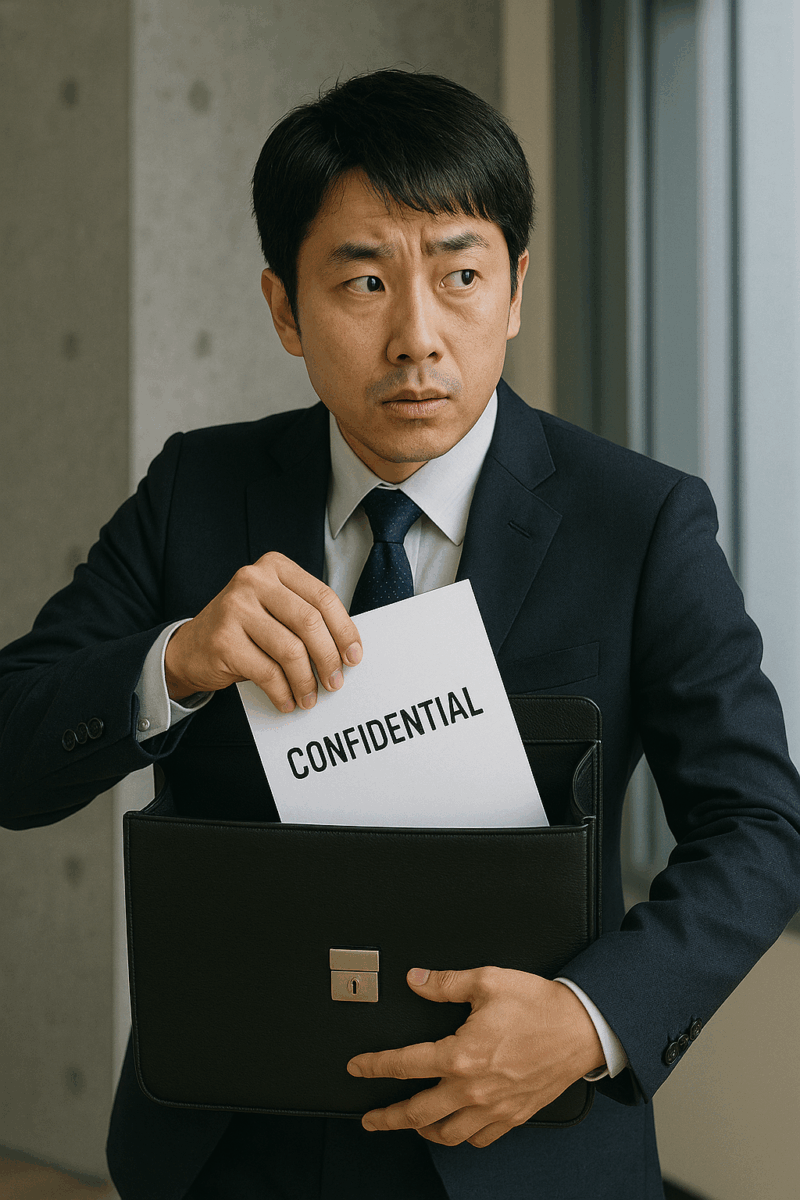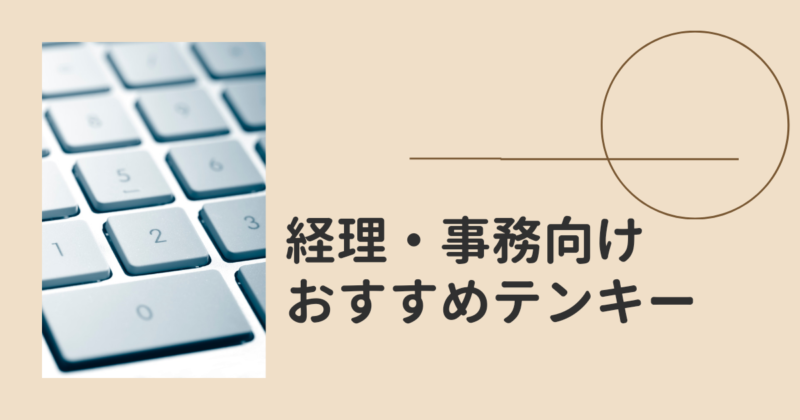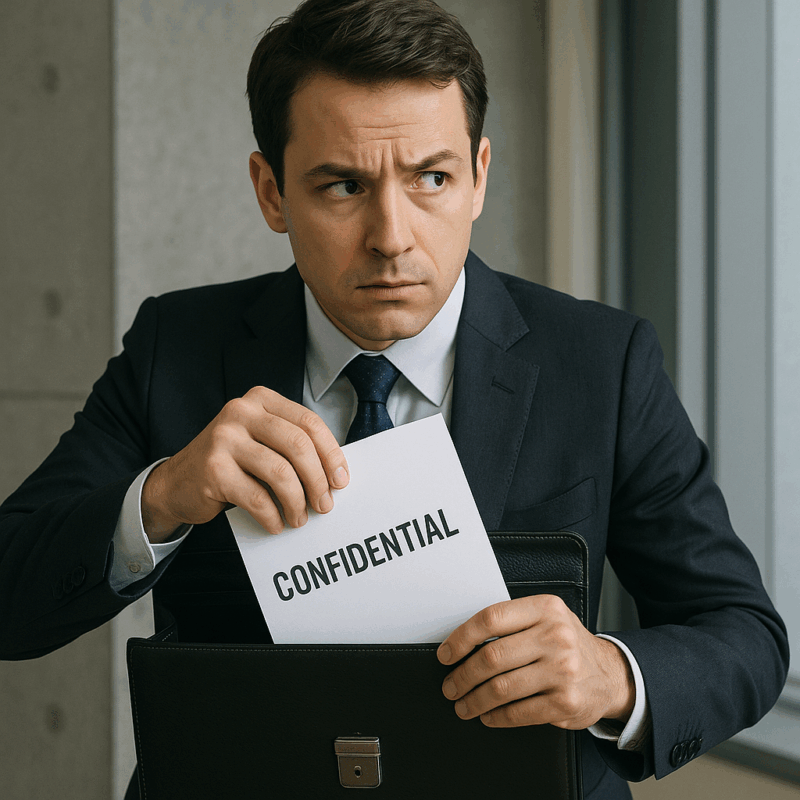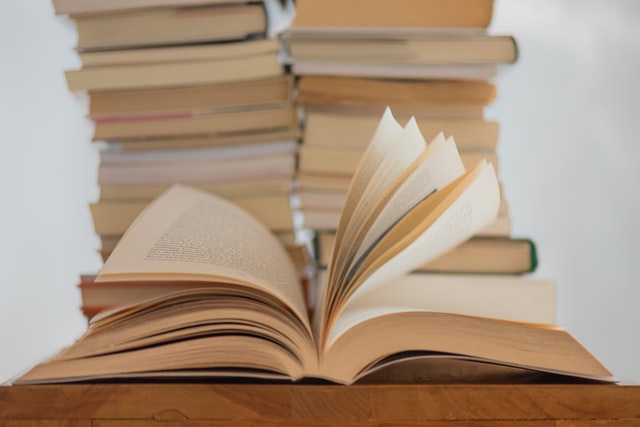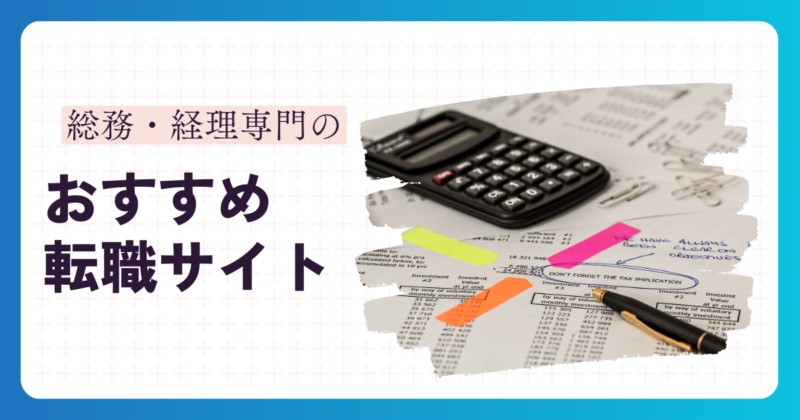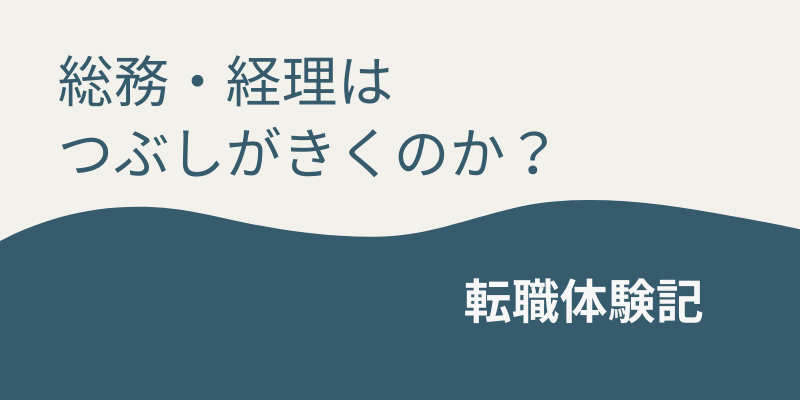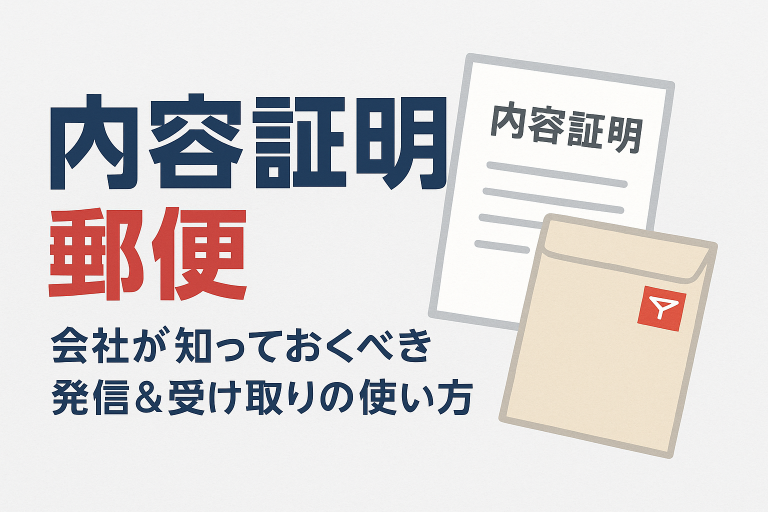
会社として「言った・言わない」で争わないため、文書で明確に意思を伝えたい――そんな場面で頼れるのが内容証明郵便です。例えば、納品遅延・未払い・雇用契約解除などの重要局面では、口頭やメールでは証拠が残りにくく、後々トラブルに発展するおそれがあります。
本稿では、総務・経理・法務担当者の視点から、会社が内容証明を発信・受領する典型的なケースを整理しつつ、書き方の基本構成・記入例・出し方・受け取った時の対応まで、実務で役立つポイントをわかりやすく解説していきます。
会社発信で内容証明を使う典型的なケース

契約違反・債務不履行の通知
たとえば、納品期限を過ぎても商品が届かない、あるいは請け負った工事が約束どおりに進んでいない場合、会社としては「このまま履行しなければ契約を解除する」といった意思表示を明確に伝える必要があります。
内容証明を使えば、催告した事実や解除の意思表示が証拠として残るため、後の裁判や交渉において大きな意味を持ちます。
売掛金・未払い代金の請求
「口頭で請求しても支払ってもらえない…」というケースは、経理担当者にとって悩みの種です。
例えば、納品から3か月経過しても支払いがなく、電話やメールでも反応がない場合、内容証明で「法的措置も検討している」旨を記載すると、相手に強いプレッシャーを与えることができます。
解雇予告・雇用契約解除の通知
労務管理では、問題行動を繰り返す社員や契約社員との契約終了に際して、通知が「言った・言わない」で争いになることがあります。
内容証明を使えば、解雇理由や通知日、解雇予定日を客観的に記録できるため、後の労務トラブルを防止できます。
例えば「勤務態度不良により30日後に解雇」と記載すれば、労基法の解雇予告義務を果たした証拠として残すことが可能です。
就業規則違反・懲戒処分の通知
従業員が横領や重大な服務規律違反を犯した場合、会社は懲戒処分を行う必要があります。
口頭での注意だけでは、後日「処分理由を知らされていない」と主張されるリスクがあります。
内容証明で「処分の種類・理由・発効日」を明記すれば、会社が正当な手続を踏んだことを客観的に立証できます。
その他(期限の催告・時効の中断)
債権回収の場面では「確かに請求した」という事実を残すことが重要です。
例えば、売掛金の消滅時効(通常5年)を中断させるために内容証明で請求を行えば、法的効力を持って時効を止めることができます。
書き方の基本構成と記入例
内容証明は「証拠に残す」ための文書なので、形式やルールを守ることが何より大切です。ここでは、書き方の基本構成と事例を交えて解説します。
必須記載項目
内容証明には以下の要素が必須です。これらを欠くと効力に疑義が生じるため注意が必要です。
- 差出人(差出人の氏名(及び会社名)・住所)
- 受取人(相手方の氏名・住所)
- 作成年月日
- 本文(通知・請求・解除などの内容)
書式・文字数のルール
| 区別 | 字数・行数の制限 |
|---|---|
| 縦書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
| 横書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
- 句読点も1字として数える
- 訂正・削除は二重線+押印が必要
👉 郵便局で様式チェックを受けるので、事前に「字数・行数」を整えておくことが大切です。
提出書類と部数
- 原本1通(郵便局保管)
- 謄本2通(1通は相手へ、1通は差出人控え)
- 合計3通が必要です。
また、送付用の封筒にも差出人と受取人を記載します。
本文の記入例と活用シーン~テンプレート集~
1. 売掛金請求の例
令和7年9月22日
株式会社XYZ
代表取締役 佐藤花子 殿
株式会社ABC
代表取締役 山田太郎
貴社に対し、令和7年7月1日納品分の代金50万円が現在も未払いとなっております。
本書面到達後10日以内に指定口座へお支払いくださいますよう請求いたします。
期限までに支払いが確認できない場合、法的手続きを取らざるを得ません。
以上
➡ ポイント:金額・納品日・支払期限を明確に記載する。
2. 解雇予告通知の例
令和7年9月22日
社員番号1234
田中一郎 殿
株式会社ABC
代表取締役 山田太郎
貴殿の日頃の勤務態度について度重なる注意を行いましたが改善が見られませんでした。
つきましては、労働基準法第20条に基づき、本書面をもって30日後の令和7年10月22日をもって解雇することを予告いたします。
以上
➡ ポイント:法律に基づいた根拠(労基法第20条など)を記載し、日付を明確にする。
3. 契約解除通知の例
令和7年9月22日
株式会社XYZ
代表取締役 佐藤花子 殿
株式会社ABC
代表取締役 山田太郎
貴社との令和7年4月1日付「業務委託契約」について、契約条項第10条に基づき、契約を解除いたします。
本通知到達をもって契約は終了するものといたします。
以上
➡ ポイント:契約解除の根拠条文を明記することで、有効性が強まる。
書き方のコツと注意点
- 曖昧な表現は避ける:「できれば支払ってほしい」ではなく「○日までに支払わない場合、法的措置を取る」と明記
- 数字や日付は正確に:未払額、契約日、解除日などを具体的に書く
- 感情的な文言は避ける:「誠意がない」「無責任だ」などは不要
👉 内容証明は「強い文書」ですが、相手を挑発するのではなく、冷静かつ事実に基づいた記録にすることが肝心です。
出し方・手続きの流れ
内容証明は「書いて終わり」ではなく、正しい方法で差し出すことが大切です。ここでは郵便局での流れと、電子内容証明の活用方法を解説します。
1. 郵便局で差し出す場合
① 取り扱いのある郵便局を探す
「集配郵便局」や主要局で取り扱いが多いので、事前に日本郵便の公式サイトで確認すると安心です。
② 書類の準備
- 原本1通(郵便局保管)
- 謄本2通(受取人用・差出人控え)
- 封筒(差出人・受取人を記載)
③ 窓口で提出・チェック
郵便局の担当者が「字数・行数・訂正方法」を確認します。
不備があると差し戻されるため、時間に余裕をもって手続きしましょう。
④ 料金の支払い
内容証明郵便は通常の郵便に比べて料金が高くなります。
料金の目安(1枚)
➡ 1枚だと合計で1,600〜2,000円程度になるのが一般的です。
⑤ 控えの保管
差出人控えは必ず社内でファイリング・PDF化して、法務・経理で共有できる状態にしておくことが重要です。
2. 電子内容証明(e内容証明)の利用
最近では、**オンラインで送れる「e内容証明」**も利用されています。
総務・経理担当者にとっては、わざわざ郵便局に行かずに済む点が大きなメリットです。
メリット
- ネットで作成・送付できる
- 24時間受付可能
- データで保存でき、社内共有が容易
- 郵便局窓口に出向く必要がない
注意点
- 事前に「e内容証明サービス」の登録が必要
- 手数料は紙より少し高め(電子送信料+利用料がかかる)
- 添付書類などは送れない(文章のみ)
👉 営業部門が地方出張中でも、本社の総務部が即座に発信できるため、スピード重視の会社には非常に便利です。
3. 配達証明を付けるべきか?
内容証明そのものは「内容を証明」する制度ですが、相手が受け取った日までは証明できません。
そこで多くの会社が配達証明付きで送付します。
- 配達証明あり:相手が受け取った日付が証拠として残る
- 配達証明なし:出した記録は残るが、受取日は不明
➡ 契約解除や債務の催告など、時効・期限が関係するケースでは必須です。
4. 実務の工夫
- 郵便局での待ち時間短縮のため、事前に体裁を整える
- 電子内容証明は、法務や経理担当とクラウド上で同時編集・承認フローを組めるので効率的
- 発信履歴をExcelや社内システムで管理しておくと後の証拠収集が容易
👉 このように、内容証明は「書き方」だけでなく「出し方」にも重要なポイントがあります。
注意点・リスク管理
内容証明は強力なツールですが、書き方や出すタイミングを誤ると逆効果になることもあります。ここでは、担当者が特に気を付けたいポイントを整理します。
1. 曖昧な表現や誤記によるリスク
内容証明は「証拠」として裁判でも利用される可能性が高いため、一言一句の正確さが重要です。
よくある失敗例
- 「○月頃に支払ってください」→「頃」では支払期限が不明確
- 金額の誤記:「50万円」と記載すべきところを「500万円」と書いてしまった
➡ 誤記があると、請求自体の信用性を損なう恐れがあります。
必ず複数人でチェックし、法務・経理・上長の承認を得てから発送しましょう。
2. 感情的な文言は避ける
「誠意がない」「裏切られた」などの感情的な表現は、相手を刺激して交渉を決裂させる原因になります。
適切な表現例
- ×「支払わないのは誠意がない」
- ○「支払期日を過ぎても入金が確認できません。本書面到達後10日以内にお支払いください。」
➡ 内容証明は冷静で事実に基づいた通知であることが求められます。
3. 法律や契約に基づかない通知のリスク
契約解除や解雇通知は、法的根拠に基づかないと無効になる場合があります。
事例:解雇予告通知
- 「本日付で解雇します」と通知 → 労働基準法第20条違反(30日前予告または解雇予告手当が必要)
- 結果として会社側が不利になる可能性大
➡ 必ず契約条項・法律条文を確認し、文中に明記することが重要です。
4. 社内承認・関係部署との調整
内容証明は外部に出る公式文書です。
勝手に担当者が作成・発送すると、会社の方針と矛盾した通知になるリスクがあります。
実務ポイント
- 経理が売掛金請求を出す場合 → 法務・営業部門と調整
- 労務が解雇通知を出す場合 → 人事部門・経営陣の承認必須
➡ 発信前に社内稟議フローを設けると安心です。
5. 送付後の対応を怠るリスク
内容証明を送って終わりではなく、送付後の対応が肝心です。
チェックリスト
- 相手が受け取った日を確認(配達証明付きなら証明可能)
- 回答期限を社内カレンダーに登録
- 入金や返答がなければ、弁護士相談や法的手続きの準備へ
➡ 送付した事実だけで安心せず、アフターフォローを計画的に行うことが大切です。
6. 相手との関係悪化リスク
内容証明は相手に「会社が本気だ」と伝える強い手段です。
一方で、取引先との関係が悪化する可能性もあります。
事例:取引先への請求
- 内容証明を送ったことで支払いはされたが、以後の取引が打ち切られたケースあり。
➡ 「すぐに裁判を検討する」という姿勢を見せるための最終手段として位置づけ、通常の交渉や督促の後に利用するのが望ましいです。
実務担当者へのまとめ
- 内容証明は「強い文書」だが、冷静かつ正確に書くことが必須
- 出す前に社内承認と専門家チェックを受ける
- 出した後も受取日確認・対応期限管理まで徹底する
👉 このように注意点を踏まえれば、内容証明は会社にとって強力なリスク管理ツールとなります。
会社が内容証明を受け取ったときの対応フロー
会社宛に内容証明が届いた場合、放置や軽視は厳禁です。内容証明は法的手続きの前段階であることが多く、対応を誤れば裁判・金銭的損失・企業イメージ低下に直結します。
ここでは、総務・労務・経理担当者が押さえておくべき実務対応を流れで解説します。
1. まずは受領確認と内容把握
- 郵便物を受け取ったら、日付・担当者・受領方法を記録する
- 受け取った封筒や証明書はそのまま保管(証拠として重要)
- 本文のコピーを取り、関係部署へ迅速に共有
事例:経理担当者が未払い請求の内容証明を受領
→ 「金額・請求根拠・支払期限」を確認し、営業・法務と連携して事実関係を整理する。
2. 関係部署で事実確認・情報整理
内容証明に記載された主張が事実か否かを速やかに確認します。
- 経理:未払金の有無・入金状況を確認
- 総務:契約書・稟議書など社内文書を確認
- 労務:就業規則・人事記録と照合
例:解雇無効を主張する内容証明
→ 労務担当は「解雇通知日・手当支払の有無」を整理し、法的に問題がないか確認する。
3. 専門家(弁護士・社労士)へ相談
内容証明は裁判前の準備行為であることも多いため、早めに専門家へ相談するのが鉄則です。
- 弁護士 → 債権回収・契約解除・訴訟対応
- 社会保険労務士 → 解雇・残業代請求など労務トラブル
注意:会社で勝手に回答文を送ると、不利な証拠を残してしまう危険があります。
4. 回答方針の決定
社内と専門家で事実関係を整理したうえで、以下の方針を決定します。
- 支払うべき請求かどうか
- 交渉で解決できるか、法的手続きに進むか
- 回答をするか、あえて回答を控えるか
例:売掛金請求の内容証明
→ 「請求は正当」「資金繰りの都合で分割払いを提案」といった交渉案を検討。
5. 回答の作成・送付
必要に応じて、回答書を内容証明で返送します。
- 請求を認める場合 → 支払日や方法を明記
- 請求に争いがある場合 → 契約書や事実を根拠に反論
- 回答を控える場合でも、専門家の指導に従い「沈黙戦略」をとることもある
ポイント:回答も証拠として残るため、冷静かつ法的根拠に基づいた文言が必須。
6. 訴訟リスクの予測と経営陣への報告
- 内容証明を受け取った時点で、訴訟リスクは高まっていると考えるべきです。
- 想定される費用(弁護士費用・損害賠償額)を見積もり、経営陣に報告。
- 必要に応じて、取締役会・経営会議で対応方針を決定。
例:残業代請求の内容証明
→ 支払額が高額になる場合、今後の労務管理体制の見直しも検討する。
7. 社内での再発防止策
- 経理:未払金が発生しないよう請求・支払管理の強化
- 労務:解雇や就業規則違反処分のフローを明確化
- 総務:契約書管理を徹底し、紛争リスクを事前に回避
実務担当者へのまとめ
- 内容証明は「会社に対する強いメッセージ」 → 絶対に放置しない
- 受領・共有・事実確認・専門家相談・経営報告をルール化する
- 回答の有無や内容は、必ず法的リスクを考慮したうえで決定する
👉 内容証明を受け取ったときの初動対応が、その後のトラブルの大小を左右します。
総務・労務・経理担当者は、**「受け取ったら即、社内共有と専門家相談」**を徹底しましょう。